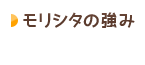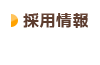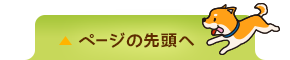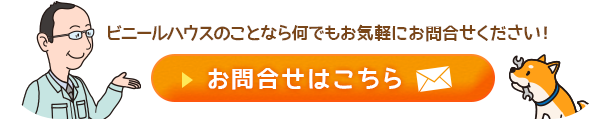農業用ハウスのモリシタの森下幸蔵です。
https://www.morishitahouse.jp/sp/(スマホ版)
https://www.morishitahouse.jp/ (PC版)
越前市 Mファーム様 ストロングXパイプハウスφ48.6の雨漏り修理レポート

修理概要
実施日: 2025年7月2日(水)
お客様: 有限会社Mファーム様
対象: 堆肥舎ハウスの雨漏り修理
施工の経緯
6月30日に越前市 Mファーム様の堆肥舎ハウスで発生した雨漏りの修理作業を行いました。
この堆肥舎ハウスは令和6年6月に完成・引き渡しを行った比較的新しい施設です。雨漏りの報告をいただいたのは令和7年2月でしたが、福井県では2月は悪天候が続くことが多いため、天候が安定する5月以降での修理対応とさせていただきました。結果として6月末の実施となりましたが、無事に修理作業を完了することができました。
ハウス仕様詳細
今回修理を行った堆肥舎は、モリシタのストロングXパイプハウス(φ48.6)を使用しています。
主要仕様:
- 間口: 10.2メートル
- 奥行き: 25.2メートル
- アーチパイプ: 大和交換工業のポストジンク φ48.6
- アーチパイプ間隔: 500ミリ
- 軒高: 3メートル(通常2メートルを高く設定)
軒高を通常より1メートル高い3メートルに設定したため、ハウス強度を確保する目的でアーチパイプの間隔を通常の600ミリから500ミリに狭めて設計しています。

雨漏り原因の調査・分析
屋根に上がって雨漏り箇所を確認した結果、フッ素フィルムの破損が原因であることが判明しました。より詳細な分析を行うため、Google AI Studioを活用して専門的な考察を行いました。
Google AI Studioへの問い合わせ
使用したプロンプト:
今回の案件では、農業用パイプハウスの屋根被覆材として、フッ素フィルムを展張しているのです。
農業用パイプハウスの棟部に防鳥線を取付ける用途のアルミ製の支柱(長さ200mm)をテックスビス止めしています。
今回、雨漏りがするので、屋根に上がって確認したところ、フッ素樹脂フィルムがしわしわになり、アルミ製の支柱周辺で破ていました。
これも温度変化による伸縮率の差が原因の可能性がありますね。考察をお願いします。
現場で撮った写真を貼り付けますので、ご確認ください。


AI分析による専門的考察
Google AI Studioによる分析の結果、今回の雨漏りは「温度による伸縮率の違い」が根本的な原因であることが明らかになりました。
問題の核心
この問題の本質は、「自由に伸び縮みしたいフィルム」を「ほとんど伸び縮みしない部材(アルミ支柱+ビス)」で一点だけ強く固定してしまったことにあります。
材料別伸縮率の比較
関係する3つの部材の線膨張係数を比較すると、大きな差があることがわかります:
- フッ素樹脂フィルム: 約 10.0 × 10⁻⁵ /℃(非常に大きい)
- アルミ支柱: 約 2.3 × 10⁻⁵ /℃(フィルムの約1/4)
- 鋼管(下地パイプ): 約 1.2 × 10⁻⁵ /℃(フィルムの約1/8)
フッ素樹脂フィルムは、アルミの約4倍、鋼管の約8倍も温度変化で伸縮することが分かります。
破断メカニズム
1. 温度上昇時(夏の日中など)
- フッ素樹脂フィルムが大きく伸びて面積が広がろうとする
- ビス固定部分は動けないため、フィルムが余って「しわ」や「たるみ」が発生
- 伸びようとする力がアルミ支柱の硬いフチ部分に集中
2. 温度下降時(冬や昼夜の寒暖差)
- フッ素樹脂フィルムが大きく縮もうとする
- ビス固定により動けないため、フィルムに強い張力がかかる
- この張力もビス穴やアルミ支柱のフチに集中
3. 繰り返しのダメージ(疲労破壊)
- 日々の寒暖差や季節変化で「伸び」と「縮み」が数百~数千回繰り返される
- 応力集中部分からフィルムが疲労し、最終的に破断に至る
対策と今後の予防法
推奨する補修・予防対策
最も効果的で現実的な解決策は、アルミ支柱とフィルムの間にクッション材となるパッキンを挟むことです。
使用材料:
- EPDM(耐候性ゴム)またはシリコンゴム製のシートやワッシャー
- ホームセンター等で入手可能なゴムシート(厚み2~3mm推奨)
施工手順:
- 破れた箇所を耐候性防水補修テープ(ブチルテープなど)で補修
- アルミ支柱の底面サイズに合わせてゴムシートをカット
- 「ビス → アルミ支柱 → ゴムパッキン → 補修したフィルム → 下地鋼管」の順で再固定
対策効果
応力緩和: ゴムパッキンがクッションとなり、フィルムの伸縮時の力を吸収・分散
防水性向上: パッキンの密着によりビス穴周りの防水性が大幅に向上
まとめ
今回の事例は、異なる材料を組み合わせる際の伸縮率の違いを考慮することの重要性を示しています。材料特性を理解し、伸縮差を吸収する「逃げ」や「遊び」を構造的に確保することが、長期的な信頼性確保の鍵となります。
このような専門的な分析により、単なる修理にとどまらず、根本原因の解決と再発防止を実現することができました。今後も科学的なアプローチを取り入れながら、お客様により良いサービスを提供してまいります。